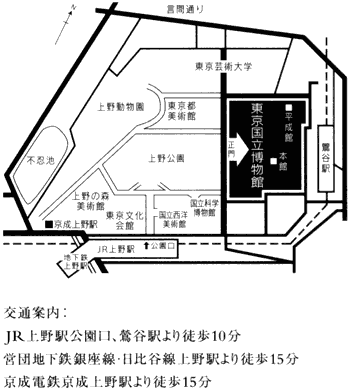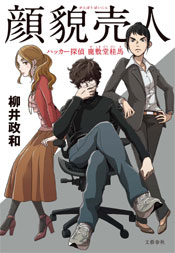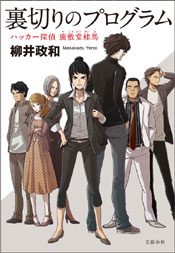●2001.10.27(土)01 東京国立博物館
2001年10月26日に、友人の aki-u 氏が上京。兼ねてよりの氏の希望通り、東京国立博物館に行ってきました。
集合は上野駅の公園口。2時に無事合流し、そのまま上野公園内を散策しながら東京国立博物館に行きました。
今回の来館は、私は初、 aki-u 氏は2回目。「前回行ったとき、教科書に載っているものがたくさんあって、非常に面白かった」と aki-u 氏は力説。私の期待も脹らみます。
上野公園は非常に広く、緑も多く、都心だと言うことを忘れるような場所でした。「ねえねえ、ここって都心からどのくらい離れているの?」と思わず質問する aki-u 氏。「いや、上野駅は環状線上だから、ここも都心だよ」思わず都心だということを忘れるような緑の多さでした。
数分歩いて東京国立博物館に到着。まずはその敷地面積の広さに圧倒されました。写真だとその広さが伝わり難いのですが、掲載しておきます。

本館は、洋式建築の上に和風の屋根、鬼瓦が乗った和洋折衷の建物。天井はとても高く、見上げるようにして館内に入りました。内部の展示スペースは1階、2階に分かれており、それぞれを見て周るのに1時間ずつかかりました。
以下、展示品の中から印象に残ったものを挙げていきます。
仏像
なかなか見ごたえがありました。仏像の時代によって、等身や体の作りが違うのが面白かったです。ただ、時代に対して点数が少なかったので、時代の特徴として個々の仏像の違いがあるのか、作者の技量の差なのかが分かるまでではなかったのが不満の残る点でした。
でも、まとめて1度に見られるので、楽しかったです。個人的には十二神将の像がユーモラスでよかったです。
刀
かなり広い面積に刀、太刀が展示されていました。どちらかというと江戸期以降の作品が多かったのですが、鎌倉時代の造りのものをありました。鞘はそっちのけで、二人して刀身を見ていました。
鑑賞自体は楽しかったのですが、できれば各刀の重量も掲載しておいて欲しかったなと思いました。実際に日本刀を持つ機会は少ないので、それぞれの重量がどの程度なのかを知りたいと思いました。
太刀は非常に重いので、私たちの腕力では振り回せないだろうなあと話しながら館内を進んで行きました。
絵画
狩野派の絵師、狩野元信の禅宗祖師図(1、2/室町時代・16世紀)は絶品でした。思わず戻って何度か見なおしてしまいました。
特に滝周辺の植物のデフォルメ具合、力強さは感動もので、緊張感溢れる画面になっていました。重要文化財なのも頷けます。
あと個人的に興味深かったのは九相詩絵巻(鎌倉時代・13世紀)です。九相詩とは、人間が死んで、その肉体が、膨れ、腐り、血や膿にまみれ、獣の餌食となり、骨だけに変わり果て、最後は土灰と化するまでの「九つの相(すがた)への想い(おもい)」を、詩にして詠みあげたものです。
いきなり他の絵の中に、死体の絵がずらーっと並んでいるのは圧巻でした。世の中には、この九相詩絵巻のスクリーンセーバーもあったりします。ちょっとお勧めです。
根付
根付(豆知識)も大量にありました。その細工の精巧さに、二人して感嘆の声を漏らしました。
他にもいろいろ、見所だらけの展示品たちでした。ほぼ2時間歩きっぱなしで館内を見て周りました。
あと気づいたのですが、来館者にはやたらと欧米人が多かったです。6~7割が欧米人でした。日本を代表する博物館なので、外国からの観光で訪れる人も多いのかなと思いました。
館内を歩き疲れたところで、ミュージアムショップに行きました。ショップは本館の地下にあり、思いのほか広かったです。記念品も多かったのですが、個人的には書籍売り場がよかったです。
書籍売り場では、美術館系の本が大量にありました。その中でもよかったのが、他の博物館や美術館でおこなわれた展示目録が売られていたことでした。たぶん余剰在庫の流用品だと思うのでですが、買い逃した方なではここで買うのも1つの手なのではないかと思いました。
最後にアクセス方法を掲載しておきます。見ての通り、非常に広い敷地面積です。