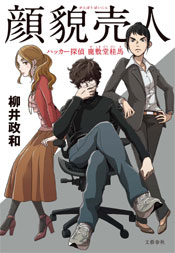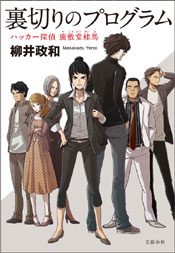● 2002.01.29(火)01 チャルトリスキ・コレクション展
現在、横浜美術館で開催中の、チャルトリスキ・コレクション展(参照:1、2)に行ってきました。今回の目玉は、何と言ってもレオナルド・ダ・ヴィンチの「白貂(しろてん)を抱く貴婦人-チェチリア・ガッレラーニの寓意的肖像画」(1490年頃)です。

白貂を抱く貴婦人
このチャルトリスキ・コレクション展は、横浜、京都、名古屋でしか開催されないそうです。こういう時、都会に出てきてよかったなあと実感します。
レオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画と言えば、モナ・リザが有名なのですが、モナ・リザは毎回図版を見るたびに、少し怖いなあという印象を受けます。そう言ったモナ・リザの印象に対して、「白貂を抱く貴婦人」は素直に美しいなあと感じました。
だいたい15世紀末期ぐらいに描かれた絵です。えてしてこの時代の絵は、現代人の感覚からすると人物や物体間の関係が激しく狂っているように感じることが多いのですが、流石にレオナルド・ダ・ヴィンチはそう言うことはまったくありませんでした。まるで今そこで振り向いたかのような自然な感じの絵で、思わず引き込まれてしまいました。
また、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の特徴なのかもしれませんが、絵を見たときに目が一点に止まらず、まるで目が絵の上を滑るかのように絵のいろんな部分に流れていきました。
多くの絵画では、画面の明るい部分で目が止まります。それに対して白貂を抱く貴婦人では、明るい部分に丁寧かつなだらかな陰影をがつけられているために、一点で目が止まることがありません。そういった効果のためか、絵を見た人間は、あたかもふと彼女を見たという自然な状態に引き込まれてしまいます。そこに、その情景があることが当然であるかのように感じてしまうのです。
モデルのチェチリア・ガッレラーニは16才の理知的な女性です。その美しい外見と、聡明な目、そして少女のような笑みを浮かべる直前の口元。
モデルの感情が表に出る直前の、内面から発露しそうな感情の一瞬の切り取りと、レオナルド・ダ・ヴィンチの確実で抑えた表現がうまく噛み合っており、長く観ていても飽きない絵でした。実際、10分以上見ていたと思います。
惜しむらくはその背景でした。元々は青灰色を基調に背景が描かれていたそうですが、絵の左上の破損を隠すために、後の時代に背景を真っ黒に塗りつぶしてしまったそうです。もったいないことをするなあと思いました。
目を瞑り元の絵を想像した後、やはり背景が黒はおかしいなあと感じました。多分、モデルの視線と絵の重みをコントロールするために、背景に光の比重の差が設けられていたのだろうなあと想像しました。
また、特筆すべきは絵の保存状態です。500年も前の絵にしては保存状態は非常に良好だと思いました。同時に展示されていた同時代の他の絵の多くが、絵の支持体が反り曲がり、絵も剥落していたことを思えば、とても丁寧に保存されていたのだろうなと思いました。
さて、白貂を抱く貴婦人だけでは勿体ないですので、他の絵の中で私がよかったなあと思う絵を挙げていこうと思います。
まずは、カルロ・クリヴェッリの「大修道院長アントニウスと聖女ルチア」(1470年頃)です。

大修道院長アントニウスと聖女ルチア
絵を見ている最中、女性が持っている椀の上の眼球に興味を持ちました。この眼球は彼女自身の眼球だそうです。逸話を読んだところ、彼女の恋人が、彼女の美しい目ばかりを見るから自分でくりぬいたそうです。怖い人もいるものだと思いました。
次はジクマリンゲンの画家の「聖セバスティアヌスの殉教」(1505-10年頃)です。

聖セバスティアヌスの殉教
次は銅板画です。マルカントニオ・ライモンディの「パリスの審判(ラファエッロの原画による)」(1515-16年)です。
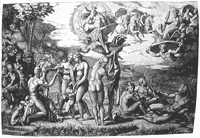
パリスの審判
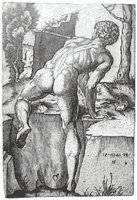
川岸を攀じのぼる男
こちらでは久しぶりに浜田知明の銅板画が見られたので嬉しかったです。とは言っても2枚しかなかったですが。以前熊本で10数点見たことがあります。ネットで調べてみたら、浜田知明は熊本出身でした。なぜ熊本で見たのか納得しました。
最後は、チャルトリスキ・コレクションのあるポーランドが誇る画家、ヤン・マテイコの「ポーランドの寓意(鎖につながれたポーランド、あるいは1863年)」(1864年)です。

ポーランドの寓意
絵自体は未完らしいのですが、この粗さが逆に熱気を感じさせているので、これはこれで有りだなと思いました。最初に見たときは、メタルギア・ソリッドの絵(参照:1)を連想してしまいました。
以上簡単ですが、チャルトリスキ・コレクション展の個人的な感想をまとめてみました。
チケット(1300円)+音声ガイド(500円)+図録(2000円)+交通費(300円)=4100円でしたが、それなりの見ごたえはありました。2時間半も絵を見ていました。楽しかったです。