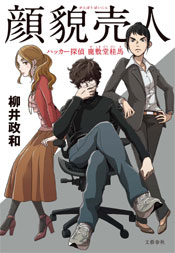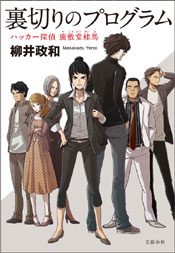● 2002.05.07(火)01 ボードゲームと私
ご容赦ください。本日ダラダラと長文です。
会社を作っても、売るものがなければ飢え死にしてしまいます。というわけで、いろいろと私の開発した物を商品化していく予定です(多分、主力商品はソフトウェアになると思います)。こういった商品化予定のものに、ボードゲームやカードゲームがあります。
日本ではあまり小規模のアナログゲーム開発・販売会社というのありません。市場自体が小さいというのもあります。市場がある程度大きくないと、その部門は不採算部門になるからです。こういう市場に参入するのはかなりのリスクを伴います。
趣味の世界とはいえ、やるからには成果を上げたいものです。そもそも、会社を作ろうと思ったきっかけは、アナログゲームの開発・販売をおこないたかったからです。
元々私は筋金入りのアナログゲーマーです。遊ぶゲームの比率から言うと、アナログ99対デジタル1ぐらいの比率です。圧倒的にアナログゲームの比率が高いです。アナログゲームは遊ぶのも作るのも大好きです。学生時代は、怪しいTRPGのルールを量産したり、PBMを運営したりしていました。
学生時代も末期、大学3年のときにいよいよ進路を決めるときが来ました。就職活動時期です。
サラリーマンで一生を過ごすの向いていないと思っていたので、アナログゲームの開発・販売会社を作ろうと思いました。
しかし、社会人の経験もなければまともなゲーム開発の経験もない、そんな状態で会社を始めて採算が取れるか。「取れる」と思うほど私は楽天的ではありませんでした。私はどちらかと言うと臆病な性格です。
そこで、社会人3年目までにおこなっておくことを決めました。
現在儲かっている業界に入り、業界の仕組みを探る
パソコンのスキルを身につける
インターネット連動のプロジェクトを運営できるスキルを身につける
メディアを持つ
ゲームデザインの理論と手法を確立させる
この項目を満たすように動き、3年経ったらサラリーマンを辞めるつもりでいました。結果的には5年弱会社にいたことになり、5年目の春、ようやく会社を興すように動き始めました。大学で言うなら2年の留年です。少しサボり過ぎたと思います。
以下、それぞれの項目に関して、どういう背景でそういうことを考えたのか、そしてその項目を達成できたのかを書いていこうと思います。
●現在儲かっている業界に入り、業界の仕組みを探る
これは実は最優先事項でした。アナログゲームの市場が狭いということは、その業界で生活できる人が限られるということです。人が少なければクオリティも上がらず、人の意識も低くなり、結果的に市場は衰退してしまいます。
何よりも重要なことは、アナログゲームの市場で儲かることです。
儲からないことは悪です。
このために、まず何よりも儲かっている業界の空気や仕組みを知りたいと思っていました。最初から儲かっていない業界に行って、その業界の空気に馴染んでしまってはいけないと考えたのです。
その他の要素(パソコン、インターネット、ゲーム)も満たす業界として、当時儲かっていた業界の1つであるコンシュマーゲームの業界に行くことにしました。
就職先はコンシュマーゲームやパソコンゲームの開発会社でした。
この項目の反省点としては、就職活動に手を抜き過ぎたことです。
就職活動を1日しかせず、大学3年のときに就職を決めてしまい、他の会社を回らなかったのは失敗でした。行くなら中小企業ではなく大企業に行くべきでした。
しかし、中小企業に行った利点もありました。ほぼ全ての仕事を一通りおこなえたことです。おかげで器用貧乏、便利屋になっているという点は問題なのですが。
仕方ないので地道な販売活動でも展開します。ゲリラ的手法だけはいろいろと学習しましたので。
●パソコンのスキルを身につける
今後アナログゲームを取り扱うにしても、パソコンとインターネットは必須の要素だと思い、そのスキルを集中的に身につけておこうと思いました。
何せ6年前の当時、私はパソコンをまともに触ったこともなかったのですから。「これがマウスか」という状態でした。初めてパソコンを購入したのは、社会人になってからでした。
この項目は、一定の成果を上げたと思っています。
結果的に拙作の「めもりーくりーなー」がオンラインソフト大賞に入賞するようになりましたので。
●インターネット連動のプロジェクトを運営できるスキルを身につける
店舗を持って、大量の在庫を抱えて商売をする手法は、個人で戦うにはあまりにもリスクの大きい手法です。
このリスクを回避するには、インターネットが非常に有効です。というわけで、インターネット連動でプロジェクトを運営するスキルが必須だと思っていました。
インターネット上での販売だけでなく、集客力のあるコンテンツを提供し、お金を得ることができるスキルです。
これは現在の所まったく成果を上げていません。無料コンテンツばかり公開していましたので。反省すべきところです。これはぶっつけ本番になりそうです(汗)
●メディアを持つ
何か新しいことをする場合、まずメディアを持つというのが、インターネット時代の重要な手法だと考えていました。
メディアには2つの効果があります。1つは告知力、もう1つは情報求心力です。遠心性と求心性の2つの効果があります。
そして何より決定的なのが、自前のメディアを持たないとインターネットの速度に乗れないことです。今すぐ知らせたいのにタイムロスがあることは、インターネット時代では死を意味します。
ではメディアとは何なのかということになります。私は「1万人以上のユニークユーザーが存在すること」と定義しています。この定義は学生時代から変わっていません。
これは「100人の法則」と私が勝手に呼んでいる法則に根ざしています。これは以下のような法則です。
何か情報を発信した場合、元々興味を持っている人の内、100人に1人はその情報を受けアクションをおこす。
何か情報を発信した場合、まったく興味を持っていない人の内、100人に1人はその情報を受け興味を持つ。
つまり、1万人(100×100)の規模を持っていれば、どんな情報でも最低1人はアクションをおこすということです。人にアクションをおこさせないものはメディアではありません。
これは、私が学生時代におこなったPBMや会誌等の発行の経験を元にした感覚的な数字です。根拠のない数字のようですが、あながち嘘ではない数字です。
こういうことを考えていたので、るてんのお部屋にコンテンツを集約させ、ユニークユーザー数を伸ばせないものかと考えていました。
結果的に現在の1日のユニークユーザー数は3000人前後なので、この項目は30%程度の成果しか上げていないことになります。少しサボり過ぎたと反省しています。ReadMeで言えば10位以内に入らないと私が定義するメディアにはなっていないことになります。
●ゲームデザインの理論と手法を確立させる
これは1年半ほど前に、実際にゲーム開発をおこなったり研究をしたりした結果をまとめて120ページほどのレポートを書きました。ゲームデザイナーズマニュアルという分厚いマニュアルです。
一部の身内にしか公開していないものです。今度立ち上げる会社名の由来にもなっています。
このレポートを書いてから、だいぶ頭の中では理論が進んでいます。そろそろ新しいレポートを書かなければならないと思っています。
この項目に関しては、アナログゲームでは8割程度の成果を上げられています。最近開発した「港の利権」や、去年開発した「マフィアの競馬」は、完全にこの理論通りに作成しました。
アナログゲームの開発・販売という一見採算の合わない分野でどうすれば採算が合うか、色々考えた結果がソフトウェアとの平行開発という業務形態でした。
アナログゲームだけで利益を上げるのはまだまだ難しいと思うので、ソフトウェアの開発と平行して食いつないでいかなければならないと思っています。
とはいえ、ソフトウェアの方でもいろいろと面白いものを出していく計画があるので期待していただければと思います。既に公開間近のソフトが数本控えていますし。
取り敢えず、年内に数本はアナログゲームを発売したいと思っています。