おすすめ
電書マンガ無料
Webマンガ
ゲームブック
闇の聖杯の儀式 電書のゲームブック
ゲーム
Little Land War... Win向けSRPG
Little Bit War Switch向け高速RTS
TinyWar... 1面数分の8bit風RTS
EX リバーシ 変形盤面、盤面多数
コミカライズ
同人活動
同人誌公開
2010年01月06日 19:47:05
1つ前の記事:[EX リバーシ] 「寅」ステージ
1つ後の記事:創活ノート 第8話「歴史本」
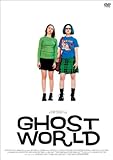 |
2001年の映画で、監督はテリー・ツワイゴフで、脚本はダニエル・クロウズとテリー・ツワイゴフです。また、主演はゾーラ・バーチで、客演はスティーヴ・ブシェミでした。
監督のテリー・ツワイゴフは、最近私が見た映画では、「バッドサンタ」(2003年)を撮っていました。
● スティーヴ・ブシェミ
この作品は「ブシェミ映画」として紹介された一本です。ブシェミは、相変わらずブシェミでした。出た瞬間に飛び道具。ただし、今回のブシェミは、ほぼ出ずっぱりです。
DVDには、映像特典で、監督らのインタビューが入ってました。
確か、監督の奥さんの話ですが、「スティーヴ・ブシェミだったら、デートに誘われたら喜び勇んでいくわ」とか言っていました。
ブシェミ大人気。
実際、映画を見ている私たちも、「きっと本人は、すごく面白くて知識豊富な人なんだろうな」と思ってしまいますし。
ブシェミは、どの映画でも同じような変な役を演じているのに、妙に印象に残って美味しいところをさらっていきます。オンリー・ワンの役者さんだなと思います。
今回、スティーヴ・ブシェミについて、Wikipediaで調べてみたのですが、昔は消防士で、今でもボランティアで消防士をしているそうです。
□スティーヴ・ブシェミ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82...
911の時にも救出に来たとか。
あの場にいた人は、ブシェミとニアミスしているかもしれないです。
● ムチムチ
映画の主人公は、高校卒業したての女の子です。彼女は、友人とともに二人で行動しています。
この二人(ゾーラ・バーチと、スカーレット・ヨハンソン)が、ムチムチでした。女子高生みたいに太かったです。
私が見る限り、女性というのは、小学生は子供で、中学生は子供の体に女の特徴が付加され、高校でドムになり、大学で女性になります。
女子高生の最大の特徴は、太い足首だと私は思っています。何というか、馬でも蹴り殺せそうな太い足を持っています。
これを見る限り、女性の成長は、ある程度までは足し算で肉を付けていき、そこから無駄な肉を削ることで成熟を向かえるのかなと思います。
だから、この映画の主人公のムチムチ感(太さ)は、高校卒業したての女の子というのを、素直に想像できるものでした。まあ、実際この時十九歳だったようで、年齢そのままの役を演じていたようなので、そういった体型だったのでしょうが。
こういった見た目は、重要だと思いました。
● 主人公の嫌悪に共感
映画はコミック原作物です。
主人公とその友人は、いわゆる悪ガキです。二人の関係は、「小さな悪の華」(1970年)や「乙女の祈り」(1994年)の二人の少女の関係に近いです。
主人公が、想像力豊かで首謀者で、相方がその付属物です。
この映画が、それらの二作と違うのは、その年齢設定です。高校を卒業して、社会に向き合わないといけない年齢に、彼女らはいます。
二人は、共同で部屋を借りようとしてバイトをしますが、主人公は長続きせず、相方はきちんと勤めて金を稼ぎます。
この二人の違いは残酷です。
学校という閉じた世界で、社会に向き合わない環境では、想像力豊かな主人公の方が主導権を握っていました。しかし、いざ社会に出てみると、主人公のような人間は、単なる社会的不適合者にしか過ぎません。
それが「金を稼ぐ」という物差しで、突きつけられます。
主人公は、自分のセンスと価値観を大切にしているけど、それは社会では何の価値も認められません。そして、それに価値を見出せない凡庸な人々を、彼女は嫌悪しています。
そんな彼女が出会うのは、古いブルースのレコードをこよなく愛する音楽オタクの冴えない中年男(スティーヴ・ブシェミ)です。
彼女は、音楽オタクの家に行き、自らの趣味と美意識で統一された部屋を見て、大いなる共感を得ます。
そして、彼に恋人がいないことで世間の女性に腹を立て、彼のために恋人探しをします。
これはそのまま、認められない自分を世間に認めてもらう代償行為になっています。
この映画を見て思ったのは、「自分の価値観が認められない」という思春期の悩みは、普遍的なものなのかということです。
ある程度普遍的なのだとは思いますが、全員が体験することではないのではと思います。
ほとんど持たない人もいれば、強烈に持ち、それを生涯引きずる人もいる。
たぶん、多くの人は引きずらないのではないかと思います。これは統計とかではなく、何となく感覚としてそう思います。
私は、いまだにそういった思いを持っていますが、多くの人はそうではないのだろうと感じています。
● 主人公の周りの人間
基本的に醜悪に描かれています。具体的に言うと、主人公の気持ちを考えずに、自分の価値観で主人公を判断したり、手を差し伸べたりするような台詞や行動ばかり取ります。
本人たちはよかれと思って、主人公が嫌いな価値観を押し付けようとします。
この人たちはみな「他人が自分と違う」ということを理解しておらず、価値観の多様性を無視しています。
主人公はそのことに苛立ちを覚え、周囲に敵意を持っています。
それが最も端的に出ているのは、この映画に出てくる美術教師です。彼女は、生徒の上辺の台詞、それも自分の好みの台詞かどうかだけで、提出作品の出来を判断します。
その作品が何であるのかは全く理解しようとせず、自分に分かる言葉だけで全てを評価するのです。
これは、この映画に出てくる大人たちを、最も端的にカリカチュアライズしている部分だなと思いました。
繰り返しギャグのように何度も繰り返すことで、その部分をかなり露骨に強調していました。
以下、中盤のネタバレが入ります。
なので、そういったのが嫌な人は、読み飛ばしてください。
● 他人の趣味をガラクタ呼ばわりする人間
映画の途中で誕生する、ブシェミの恋人ですが、これが他人の趣味をガラクタ呼ばわりする人間です。
そのことに、主人公は立腹します。
たぶん、この恋人のような人が、他人の物を断りもなく捨てたりするんだろうなと思いました。それって窃盗です。
こういう観点から見て、人間の付き合い方には三種類あると思います。
価値観が合う人。価値観が合わず、自分の価値観だけで物事を判断する人。価値観が合わず、でも他人の価値観を認められる人。
一番目と二番目の人は、実は同じ可能性がある。価値観が合っているうちはよいけど、価値観が合わなくなると、他人を認められなくなる可能性がある。
なので、他人と付き合う際は、そういった部分も見定めなければならないだろうと思います。
映画では、この「ガラクタ呼ばわりされた」というシーンが非常に印象的に頭に残りました。
● 主人公のスケッチ
主人公は常にスケッチブックを持ち歩いて、自分の目を通した世界をイラストにしています。
その絵は上手いのですが、美術の先生の好みには合わないので一切認められません。
このスケッチブックは、映画全体のメタファーになっていると思いました。「世界は、彼女の目を通して見れば、他人とは違うように見える」という仕掛けです。
この「スケッチブックと、それを通した世界の見え方」という構造は、そのまま終盤の伏線になっています。
映画を見終わった直後は、単なる小道具としての伏線だとしか感じませんでしたが、今回感想を書くために、映画のシーンを一つずつ思い出していると、それが主人公の視点のメタファーになっているのだと気付きました。
スケッチブックには、主人公の目に映る世界の変化が写し取られていました。なるほどなと思いました。
● 粗筋
以下、粗筋です(ネタバレあり。最後まで書いています)。
主人公は、高校を卒業したばかりの女子。彼女は悪戯好きの少女で、友人の少女とともに、悪さばかりをしていた。
彼女はある日、変な中年男に悪戯をしかける。そして、その成果を見るために、その中年男に会いに行ったことで、その男に興味を持つ。彼は、自分だけの世界を持ち、それを育んでいたからだ。
主人公は、彼と親しくなり、彼の趣味についてもよく知り始める。彼は、古いブルースマニアで、多くのレコードを所有していた。そして、彼の部屋は、彼の美意識で統一されており、その世界に彼女は共感を抱く。
彼が世間で認められないのはおかしい。それは、彼女自身がおかれた現状への叫びでもあった。
友人と部屋を借りるためのバイトは長続きせず、家では父親の再婚相手と反りが合わない。学校は卒業前に補習を受けさせられ、その授業を担当する美術教師の底の浅さに、主人公は呆れ果てる。
主人公は、音楽オタクの中年男に彼女を作ろうとするが上手くいかない。しかし、ひょんなことから、彼に恋人ができ、彼女はお役ごめんとなる。
そのことで、主人公は中年男が好きだったことに気が付く。そして彼女は、強引に中年男と肉体関係を結び、恋人と別れさせる。
しかし、肉体関係を結ぶことで、彼女のなかでは何かが変わってしまった。彼女は男の許から姿を消す。男は必死に彼女を探す。二人は再会するが、彼女は男を置いて町を出る。
1つ前の記事:[EX リバーシ] 「寅」ステージ
1つ後の記事:創活ノート 第8話「歴史本」
















